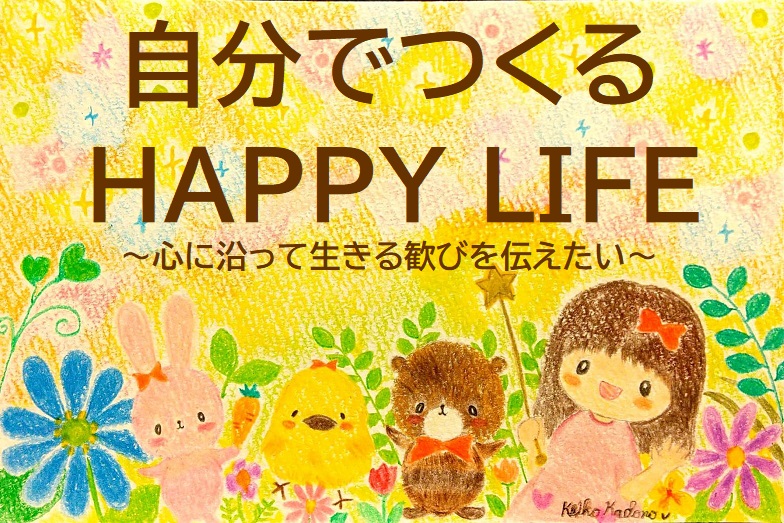湿疹や皮膚炎がなかなか治らない・・・
かゆくてつい掻いてしまう・・・
アロマオイルがいろいろな症状緩和に役立つって聞いたことがあるけど、湿疹や皮膚炎に効くものもあるのかな?
こんな風に期待して、こちらの記事を読んで下さっているのだと思います。
結論から申しますと、湿疹や皮膚炎に対しても、アロマオイルは活用することができます。
ですが、それには押さえておきたいポイントがあるんです。
この記事では、
「湿疹や皮膚炎に伴う痒みの緩和と身体の治癒力を高めるために、アロマオイルをどう役立てることができるか」
看護師としてや自身の体験、アロマセラピストとしての知識、専門家に教えていただいたことを踏まえて記事に残します。
湿疹や皮膚炎をアロマでケアしたいあなたに知っておいてほしいこと
さきほど、
「湿疹や皮膚炎に対してもアロマオイルは活用することができます」
とお伝えしました。
確かにそうなのですが・・・
実は湿疹や皮膚炎そのものを治す効果があるアロマオイルはありません。
まず、ここはしっかり理解しておく必要があります。
ですが、アロマは使い方次第では、湿疹や皮膚炎の悪化を予防するのに役立てることは可能なんです!
そこで、カギとなるのが、
・痒みへの対処
・治癒力を高める
この2点です。
上記2点のためのケアにアロマお取り入れていくことがおすすめなんですね。
痒みの原因はいろいろとありますが、日常的に症状があると本当に辛いです。
部位や範囲によっては、見た目にも気になりますし・・・
湿疹や皮膚炎への具体的なケアの方法の前に、まず知っておきたいことをまとめますね。
使う精油について
この記事では、タイトルにも記事導入部分にも、わかりやすいように「アロマオイル」と記載しています。
ですが、実際ケアに使用するのは「アロマオイル」ではなく、「エッセンシャルオイル(精油)」と表記されているものになります。
ここはとても重要なので、購入時はご注意ください。
その他、アロマテラピーを行う上での注意点についてこちらにも記載していますので、ご一読ください↓
皮膚には本来健康を保つ機能がある
皮膚トラブルがあると、ついつい外から何かを与えてどうにかしようとしがちではないですか?
けれども、本来は皮膚そのものに健康を保つ機能があります。
なので、ケアをする際は過剰にはせず、足りない部分を補うという考え方がベストかと思います。
というのも、過剰にあれこれ外から与えすぎてしまうと、本来の機能を妨げることにもなるからです。
まず、皮膚にはどんな機能があるのかをみてみましょう。
私が愛読している「今すぐ使えるメディカルアロマセラピー(MCメディカ出版)」には、皮膚の機能についてこう書かれています。
触覚、痛覚、温覚、冷覚、圧覚を中枢に伝える知覚作用、汗や皮脂などの分泌物wp身体の外へ出す分泌排泄作用、その他いろいろありますが、一番大きな作用は外部から身体を守る対外保護作用でしょう。衝撃から身体を守るクッションとしての役割、水分などを内部へ侵入させない役割、酸性を維持し細菌や真菌の侵入を防ぐ役割、体液の損失を防ぎ、光線から身体を守る役割までしています。
このように、皮膚の健康を守るのに、十分過ぎる機能が既に備わっているんですよね。
ちなみに、湿疹や皮膚炎は、皮膚の一番上の表皮における炎症性変化を言います。
そして、外からの刺激、体質、ホルモン、ストレスなどの影響により生じます。
湿疹や皮膚炎を直接は治せない。でも痒みの緩和には精油が大活躍!
ここでは、痒みに対してそれぞれどんなアプローチをしたのか、また有効と言われているのか、自身の体験とメディカルアロマテラピーの授業で私が講師より教えてもらったことをまとめています。
まずは、痒みを伴う湿疹や皮膚炎でよくあるものをピックアップしました。
ケアをする上での参考に、少し整理してみましょう。
1、接触性皮膚炎(かぶれ)
接触性皮膚炎は、いわゆるかぶれですね。
洗剤や薬品などの刺激で起こるものもあります。
そして、皮膚に付着してすぐか、遅くても翌日には何らかの反応があります。
また、そんなに強い刺激ではないけれども使い続けた結果皮膚症状が表れるものもあります。
接触性皮膚炎にはアレルギー性皮膚炎もあって、アレルギーの原因物質に対して抗体のある人に起こります。植物や薬、金属類などがあります。
皮膚に塗っている物質が紫外線に反応してかぶれたりするものを、光接触性皮膚炎と言います。
アロマテラピーを少しされている方ならご存知かと思いますが、精油にも光毒性と呼ばれる反応を起こすものがありますよね。
光毒性は柑橘系の精油に多く、皮膚につけて紫外線を受けると酸化して皮膚の刺激となってしまいます。
私は昔はわりと皮膚が強かったように思うのですが、年齢が上がるにつれ敏感になってきました。
・過剰にケアをし過ぎたこと
・ストレスを溜め込んでいたこと
・仕事柄不規則な生活になっていたこと
・睡眠不足
以上が、私の場合大きく影響しているのではないかなと思っています。
というのも、今は上記4つが解消されていて、やはり当時に比べると過敏ではなくなっていると感じているからです。
ですが、少し生活が崩れ出すと、ストレートにお肌の調子が悪くなるのもわかります。
私の場合、疲れた時はよく潜在に反応していました。
赤く盛り上がった湿疹(膨隆疹)がぶわ~と出るんですね(^^;)
で、とても痒い・・・
こうゆうかぶれに対しては、ジャーマン・カモミールの精油が役立つとされていて、私はハーブティとして売られているジャーマン・カモミールを煮だしてローションにしてスプレーしていました。
す~として気持ち良いです^^
2、乾癬
乾癬は原因ははっきりしておらず、体質的なものが大きく伝染はしません。
ストレスや刺激の有無などにより良くなったり悪くなったりを繰り返します。
部分的に赤く盛り上がって一番上には乾燥して白くなっているところがあり、垢として剥がれ落ちます。
完全に治すのは難しいですが、フランキンセンスの精油を用いたケアは良いとされています。
乾癬の皮膚症状は、関節の外側(伸びる方)や、体幹では背中の方にみられます。
私の場合、右手親指の付け根部分の関節のところに乾癬があります。
確かに、症状が強くなったり軽減したりを繰り返していて完全に治ることはないですね。
ただ、かなり落ち着いた状態を保つことはできています。
痒みが強くなる時は、少し気持ちがイライラしていたり不安を感じている時とか、体調を崩しているような時が多いです。
そして、困ったことに無意識に掻いてしまうんですよね。
案の定、その後は悪化して少し広がってしまいます。
上記にはフランキンセンスとありますが、私のところではあまり常備していない精油なんです。
で、乾癬にはジャーマン・カモミールも有効なものの1つになっているので、かぶれの時と同じくハーブティでローションをつくってスプレーしています。
その他、ワセリンをうすく塗って対処することもあります。
ワセリンは外の刺激から肌を守り、体内の水分が蒸発するのを防ぐ膜のような役割を果たしてくれます。
その為、肌の機能がスムーズに働けるような肌環境をつくることができます。
刺激から守ってくれるからか、痒みも少しましに感じられました。
ワセリンケアは長期的なケアよりは、必要最小限かつピンポイントでごく少量使用に向いています。
3、アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎にもいろんな状態がありますが、部分的ではなく全身的に起こります。
特に関節が曲がる内側、体幹であればお腹側にみられます。
原因ははっきりとしていませんが、お母さんのお腹の中にいる間の食べ物の影響は大きいとされています。
生まれてからは、生活習慣の調整、ストレスケア、皮膚への刺激を避けるなどにより症状をコントロールします。
かゆみは局所だけでも辛いので、それが全身的になると本当にたまらないはずですよね。
症状があまりに強い時には、西洋医学に基づいた治療が最優先です。
ですが、アロマテラピーでもアトピー性皮膚炎の症状緩和に役立つとされている精油や方法があります。
私自身はアトピーはないのですが、メディカルアロマテラピーの講師より教えていただいたことを以下にまとめました。
まず、アトピー性皮膚炎になっている皮膚はどのような状態になっているのかを整理してみましょう。
「今すぐ使えるメディカルアロマセラピー(MCメディカ出版)」には、アトピー性皮膚炎についてこう書かれています。
アトピー性皮膚炎の患者さんは。強いかゆみのため、ただでさえ防御機能が落ちている皮膚にひっかき傷をつくって、さらに防御機能を落としてしまいます。そしてさらに強いかゆみとなり、またかいてしまうという「かゆみの悪循環」を形成することになり、症状がどんどん悪化してしまいます。
防御機能の低下しているアトピー性皮膚炎の患者さんの皮膚、特にジュクジュクした部分では、健常人と比べ、黄色ブドウ球菌、時にはMRSAなども付着し増殖することが多く、それらの最近の出す毒素で症状が悪化すると言われています。
ですので、アロマテラピーを取り入れるとしたら、皮膚表面の細菌に対して、抗菌・殺菌作用の高いテイートリーの精油が役に立ちます。
ワセリンにラベンダー精油と、ティ―トリ―精油を混ぜてうすく塗る方法などがあります。
その他、炎症を鎮めてくれる作用をもつジャーマン・カモミールにより全身のトリートメントも役立ちます。
ちなみに、カモミールには、ジャーマンとローマンがあります。
どちらも炎症を抑える作用を持ち合わせますが、特におすすめとされているのはジャーマンです。
カマズレンというのが含まれていて、炎症を鎮めるのに優れた作用があると言われています。
ジャーマンもローマンも見た目はよく似ていますが、花の大きさはローマンの方が大きいです。
そして、香りもローマンの方が甘酸っぱいリンゴをイメージさせる感じで楽しめるかなと思います。
ただ、ローマンは苦味があるので、ハーブテイ―としてメジャーに使われるのはジャーマンです。
私はアトピー性皮膚炎に対する、ジャーマンカモミールを用いたトリートメントの効果を経験したわけではありません。
しかし、実際に何人ものアトピー性皮膚炎で悩んでいる人にトリートメントを行なったアロマセラピストによると、
「ジャーマンカモミールを用いてトリートメントを継続した結果、程度の差はあれ、みなさん何らかの改善がみられた」
とのことです。
ただし、浅い知識で自分で毎日トリートメントを行うとなると、状態を悪化させる可能性もあります。
その為、トリートメントしてもらうのであれば、やはり専門知識を有する人にしてもらうことを強くおすすめです。
家庭で比較的安心して取り入れるケアとしては、上記でも少しご紹介しましたが、ハーブテイ―のカモミールをローションとして用いる方法です。

少し濃いめに煮出したジャーマン・カモミールテイを冷まして、かゆみのある分部にスプレーする方法ですね。
つくったローションは、冷蔵庫で保存し、できるだけ早く使いきります。
アトピー性皮膚炎にしても他の皮膚炎にしても、かゆみが伴うと掻いてしまって悪化するケースは非常に多いですよね。
ですから、かゆみを緩和させることは、皮膚状態の悪化を防ぐ上でとても有効と言えるでしょう。
虫刺されなどのピンポイントのかゆみに役立つ精油は?
夏場など、ちょっと夕方に外に出るとすぐ蚊に噛まれてしまいますね(^^;)



虫刺されなどのピンポイントのかゆみに対しては、局所麻酔の作用を持つペパーミントの精油が役立ちます。
私は、ラベンダーとペパーミントの精油を無水エタノールと精製水で希釈したスプレーを持ち歩いていて、痒いところによくスプレーしています。
とても役に立っていて助かっています。
ラベンダーとペパーミントのスプレーは、頭痛緩和、乗り物酔い予防、リフレッシュ、風邪や花粉症予防など、かなり重宝しています。
詳細はこちらの記事にまとめています。
ペパーミントの精油は、範囲の広い部位には向きません。
また、あまり継続すると、乾燥を引き起こしてしまいますので注意が必要です。
湿疹や皮膚炎のアロマケアのポイント!かゆみ緩和以外にできることは?
すぐに食べられる便利な食べ物や欧米化した食生活。
強力な効果がある洗剤や化粧品など様々なもの。
役立つもの、便利なものが増え、生活面で現代はとても豊かになりました。
しかし、その分体に負担をかける面もありますね。
本来の生体リズムがバランスを崩したり、自然治癒力が抑え込まれてしまっているようなところもあります。
その為、これまで少なかった病気や心身のトラブルが増えているのも事実です。
身体本来の機能が落ちるということは、当然皮膚も同じですよね。
身体本来の機能が十分働けない状態では、せっかく外からいろいろケアしても、一時的なものとなってしまいます。
ですので、ここでは身体の機能が上手く働き、治癒力を高めるためにできることのお話をします。
私たちの身体には、一定のバランスを保とうとする恒常性(ホメオスターシス)の仕組みがあります。
そして、「1回で受かる!アロマテラピー検定1級・2級 テキスト&問題集」にはこう書かれています。
過度のストレスや不規則な生活が続くと、この仕組みが正常に働かなくなり、病気を引き起こすことになりかねません。身体が本来もっている機能を十分に発揮するためには、栄養・運動・休養という3つの大きな柱を軸に身体づくりを考えることが大切です。
これはごく当たり前の内容かもしれません。
ですが、心身ともに忙しい毎日を送っていたりすると、意識が向かない人も多いのではないでしょうか。
もしかしたら、流行の健康法はしているけど、栄養・運動・休息という基本的なことが案外偏っているという人もいらっしゃるかもしれません。
あるいは、勉強しすぎてカチカチに頑張りケアをやり過ぎているという人も。
これだと、かえって本来の機能を奪うだけでなく、ストレスを感じることにもなりますね。
私も、妙なこだわりをもち、自己流の健康法を思い込みでしていたことがあります。
看護師のくせにお恥ずかしい話ですが(^^;)
1、栄養・運動・休息
食事については、有機野菜やお魚中心で、発酵食品を取り入れたりといった和食が良いです。
腸内環境を整えることがとても大切になります。



その他は、適度な睡眠と運動も大切ですよね。
特に、睡眠による影響はテキメンにあらわれませんか?
以前フルで働いていた時は、常に寝不足・浅い睡眠でした。
なので、睡眠がしっかりとれている時とそうでない時の差があまりわかっていませんでした。
けれども、今は睡眠時間も質も確保できるようになった今は、そのバランスが崩れると、途端に体調が悪くなるんですね(^^;)
めちゃわかりやすいです。
そして、やっぱり睡眠の働きって重要やなと思いました。
2、刺激を避ける
アトピー性皮膚炎のある人は特に、刺激を避けるというのも重要ですね。



具体的には、やさしい肌触りの衣類やリネンを選んだり、肌につける化粧品や洗剤類などの選び方に注意します。
低刺激や赤ちゃん用など表示されているものもありますが、それらも合成洗剤です。
固形の純石鹸は、 表面の汚れは落としてくれますが必要以上に肌の成分を奪うということはなく、時間が経つと肌の機能に潤った状態に戻ります。
柔軟剤や化粧品、臭い消しなどすごく強力ですぐに効果を実感できるものは、それだけきついということでもあります。
なので衣類やリネンに使用した場合でも汗と一緒に肌についたりするとかなりの刺激になるので注意が必要です。
3、ストレスケアも忘れずに!
あと、重要なのがストレスのケアですね。
食事や運動、休息の話とも重なりますが・・・
乾癬もアトピー性皮膚炎の症状悪化には、食事・睡眠・生活リズムの他心の状態がかなり影響を与えます。
また、毎日の生活の中で、精神的ストレスを感じる要因となることはいくらでも出てきます。
ですからその都度自分自身の心に目を向けてセルフケアを継続していくことは大切になります。
ストレスが及ぼす影響や、ストレス発生の仕組み、ケアの方法についてはこちらの記事にまとめています↓
まとめ
いかがでしたか?
湿疹や皮膚炎をアロマオイルでなんとかしたいと思って読んで下さった方には、アロマでは治せないと書いているのをみて残念に思われたかもしれませんね。
けれども、湿疹や皮膚炎の発生や悪化の仕組み、皮膚の本来の機能を知った上で、アロマ(精油)を効果的に取り入れていくことはできます。
かゆみの緩和もそうですが、睡眠の質改善やストレスケアにアロマテラピーを取り入れていくのも良いですよね。
また、精油は天然素材でとても優しいからと、病院などで処方されるお薬などの代わりとして使ってる人もいますよね。
それぞれ個人の責任においてするなら良いかもしれません。
しかし、天然だから優しいというのは勘違いです。
アロマテラピーで用いる精油には、薬理作用があり、その1滴に含まれる作用はかなり濃厚です。
なので、適切な量、方法で取り入れればとても役立つものなのに、誤った取り扱いにより残念な結果になってしまうこともあります。
ですので、精油の取り扱いの注意点を十分理解した上での活用をおすすめします。
なぜこんなにうるさく書いているかというと、実際私の周りにも、皮膚に直接塗ることを許可されていない精油を原液で普通に皮膚に塗っていた人もいらっしゃるからなんです。
またエッセンシャルオイル(精油)ではないものをを間違って使用して、アロマテラピーを行って効果がないと言っている人も。
その他、ビンの開封から何年も経ったものを使ってケアしているとか・・・
幸い大事に至ったケースはあまりありませんでしたが、期待する効果が得られた人もいませんでした。
くどくどと書いてしまいました(^^;)
とは言え、あらゆる面においてアロマテラピーは何かと役立つのは事実。
正しい知識のもと上手く活用していけると良いですよね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。